5月3日に撮影した「おおぐま座」のM101(回転花火銀河)の画像があまりにひどかったので、5月18に再度撮影し、その画像をプラスして画像処理してみました。
ただ両日共に薄雲があり、空の条件はよくありませんでした。
また、高感度で撮影したにもかかわらず、5月3日分の画像はCMOSカメラの冷却ができていません。
なのでノイジーで、ボヤーとした感じの画像になっています。
前出の画像よりは多少ましかな。
《撮影データ》
2022年5月3日/5月18日
R200SS+エクステンダーPH+ASI533MC Pro /CBP+UV/IRカットフィルター/SX2赤道儀+ASI122MM-mini+ステラショット2(オートガイド+撮像)
GAIN:450/85~135秒×47コマの加算平均コンポジット/ダーク補正:12コマ/フラット補正:15コマ




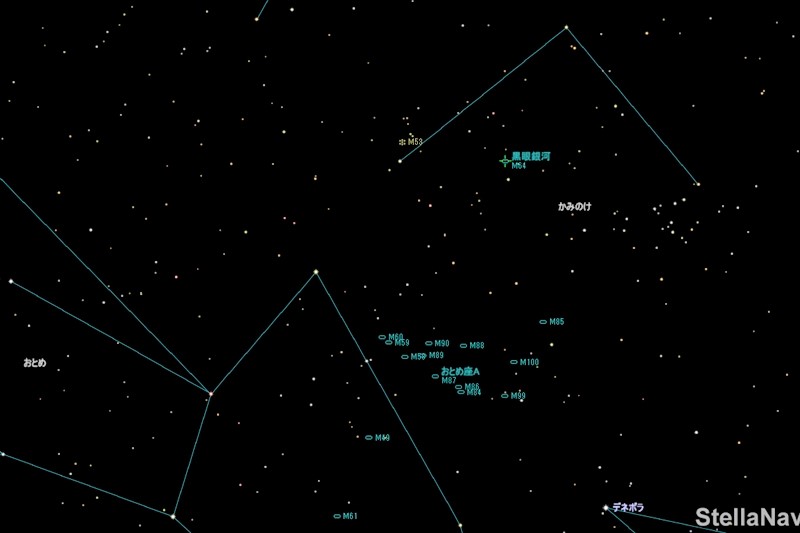 《撮影データ》
《撮影データ》